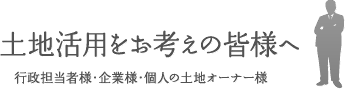当協議会では全国各地の皆様方からのご相談・ご質問をお受けしておりますが、中にはかなり似通った内容のものも多々ございます。
そこで、話題性・共通性のある内容をご紹介していきたいと思います。
ご参考になれば幸いです。
お答え頂くのは定期借地権に関して造詣深い弁護士の江口正夫先生です。
※直接、江口弁護士へのお問合せ等は堅くお断り致します。
第1回(2008.08)
-
借地人Aは地主Bから旧借地権で土地を借り、A所有の建物に長く住んでいたが、老朽化したため建て替えの承諾にお願いに行った際、地主Bから、『承諾料の請求の替わりに50年の定期借地権で再契約をしよう』と持ちかけられた。
保証金も取らず、地代も今までの更新内容を引き継ぐとの事で、子供に財産を残さない主義の借地人Aの理にもかなう為OKしたいと考えた。
A・Bとも問題は起きないか?
-
旧借地権を設定していた場合に、借地上の老朽化した建物を取り壊し、新たに建物を新築した上、50年の定期借地権を設定するというケースですが、旧借地契約を定期借地契約に切り替える合意は無効とされています。
その理由は、旧借地権を設定していた土地は現在も旧借地法が適用されており、定期借地権の根拠法である借地借家法は適用がないからです。
これを有効に行うためには、まず当事者間で旧借地契約を合意解約し、旧法上の借地権を消滅させた後に、当事者間で新たに定期借地権を設定するということになります。
旧借地権を合意解約する際に、金銭的な補償を一切行わないことが有効か否かについては、見解がわかれるところだと思います。
第2回(2008.09)
-
会社Aは地主Bから20年の事業用借地権で土地を借り、店舗を建てようとしているが、会社Aは事業が将来順調ならば環境や交通至便等から出来れば長く借りたいと考え、『甲・乙協議の上、再契約できるものとする』という文を最初から公正証書に記載したいと考えているが可能か?
また、最初の公正証書には記載されてはいなかったが、存続期間の満了前に再度新しい借地権を設定する旨の予約を結ぶ事は可能か?
-
-
「甲・乙協議の上、再契約できるものとする。」との条項は、あってもなくても法的効力に変わりはありません。
なぜなら「協議の上、再契約できる」との条項は、協議が成立しない限りは(即ち、甲と乙が再契約を合意しない限り)再契約ができないということですから、合意しない限り再契約ができないというのは当たり前のことであって、契約書に盛り込む意味がありません(但し、誤解に基づくものと思われますが、「協議の上、再契約できる」という条項があれば、協議をして再契約をしてもらえるものと考える当事者が少なくなく、実際にはこの条項でスムースな解決が図れている場合もないわけではありません。相手方に法的知識があればこの条項は何の役にも立たないことになります。)。
- 最初の公正証書には記載されていなくとも、存続期間の満了前に再度新しい借地権を設定する旨の予約契約を締結することは法律では禁止されておりませんので、十分可能であると考えられます。
第3回(2008.10)
-
50年の一般定期借地権を結んで借地人AはA所有の建物を建てて住んでいたが、設定後35年目に火事で建物を消滅した為、また高齢で再築して土地を使用する意欲も資力も無い為、借地人Aは一方的に定期借地権を放棄したいと考えたが問題はないか? また、上記の場合での賃借権の放棄の場合と地上権の放棄の場合との違いはあるのか?
-
-
定期借地権の存続期間中に建物が火災等で滅失し、借地人が再築の意欲も資力もない場合に一方的な権利の放棄ができるか否かということですが、まず定期借地権設定契約に期間内解約条項があれば、この規定に従って解約をすることになります。期間内解約条項がない場合は、地主と協議の上、合意解除をすることになります。
ただし、期間内解約条項がなく、地主が合意解除に応じない場合には、定期借地権の一方的な放棄ができるかということが問題になります。権利に関する一般的な原則として、権利の放棄は権利者の自由と考えられています。しかし、その場合は権利を放棄することは可能ですが、定期借地契約の場合には権利だけではなく義務(地代支払義務)がありますので、その義務は当然には放棄できないことになります。したがって、結論としては、定期借地権の一方的な放棄は不可能であり、合意解約を取り付けるしかないと考えられます。
- 賃借権の放棄と地上権の放棄の差があるのか否かということですが、賃借権において一定期間ごとに賃料を支払う場合には、上記のとおり放棄は不可となりますが、地上権において一時金を支払い済みで地代が発生しない地上権の場合には、放棄が可能な場合があり得ると思われます。
第4回(2008.11)
「定借用地における根抵当権の設定」について、3つの質問をします。
-
定期借地予定地に土地所有者側の根抵当権が設定されているが、このまま土地を借りた場合、当方の融資予定銀行に影響はあるか?
また借地期間中に当方に起こり得る事柄があるとすればそれは何か?
-
根抵当権が設定された土地を、抵当権が設定されたままの状態で借地すると、将来、地主が金融機関に対する返済が滞り根抵当権が実行されると(定期借地権を設定した土地が競売にかかる)、土地に設定された抵当権は定期借地権に優先していますので、定期借地権は契約期間中であっても消滅してしまいます。
このため、定期借地の実務では、底地に抵当権が設定されている土地については、定期借地権は設定していないということが絶対の原則になっています。
お問い合わせの、「当方の融資銀行に影響はあるか」との点ですが、当然ながら借地人側の融資銀行は、底地に根抵当権が設定されていれば融資に応じませんし、万一、審査の甘い銀行があったとしても、地主が金融機関に対する返済が滞って根抵当権が実行されると、借地人側は建築した借地上の建物は解体撤去して土地を明け渡さなければならなくなります。
-
土地所有者側に根抵当権をはずして欲しい旨を話してもよいのか?
-
当然ながら、根抵当権がついたままでは定期借地権の設定は絶対に出来ない旨は地主にはお話しています。
実務上は、地主に別担保を地主側の金融機関に提供して当該土地の根抵当権をはずしてもらうことは可能かというお問合せはしています。
-
相手方が新たに根抵当権又は抵当権を設定しようとした時、事前に連絡があるのか?
拒否することはできないのか?
-
定期借地権を設定した後に、地主が底地に根抵当権等を設定する際に事前に借地人側に連絡がくることはありません。それは、実務上は前記のとおり、定期借地権を設定する土地には抵当権が設定されていないからで、定期借地権設定後に地主が底地に抵当権を設定しても、この場合には定期借地権のほうが抵当権に優先しますので、仮に抵当権に基づく競売が実行されても、定期借地権はそのまま存続するため、借地人側に法的な不利益がないからです(競売により地主が交替することにはなりますが、土地を使用させる債務の履行には問題がありません。)。
逆に、本件のように先行する根抵当権が存在する場合には、定期借地権を設定した者は、地主側の根抵当権が実行されれば、何時でも建物を取り壊して退去する意思で土地を借りたとしか評価されませんので、後の抵当権の設定を拒否することもできません。
第5回(2008.12)
建物譲渡特約付定期借地権を設定して、建物所有を目的とした土地の賃貸借を検討しています。
A社と契約を取り交わすものと仮定します。建物に所有権移転請求権の仮登記を行います。
-
A社が建てた建物に、借地権設定期間中にA社が抵当権を設定し、金融機関から融資を受け、借地権設定期間満了時の建物譲渡時にも融資返済が済んでおらず、抵当権が残ったままの建物譲渡を受けることになった。当方が代価弁済又は抵当権消滅請求により抵当権を消滅させることもできると思いますが、抵当権者との間で合意に至らなかった場合、抵当権の実行により競売、競落者のために法定地上権も設定されてしまう。 と、このようなストーリーは起こり得るでしょうか?
なにか制限する方法はあるのでしょうか?
-
建物譲渡特約付借地権に基づき借地人が建設した建物に金融機関の抵当権が設定されている場合に、譲渡特約実行時に抵当権が残存していた場合は、譲渡特約の実行後に抵当権による競売、競落者のための法定地上権の設定等に対してどのような対処が可能かという御質問ですが、建物譲渡特約付借地権を設定した際に建物に譲渡特約についての仮登記を経由していると思います。建物は譲渡特約付借地権に基づいて建設されるものですから、譲渡特約についての仮登記は本来的には他の権利に優先して設定されるべきものですが、この仮登記が抵当権の設定登記よりも前に設定されていれば、仮登記の順位保全効力により30年後に実行される建物の譲渡は、それ以前から設定されていた抵当権に優先することになりますから、譲渡特約の実行により抵当権設定登記は抹消請求により抹消することが可能です。仮に、金融機関との力関係から、抵当権の登記が最優先で設定され、譲渡特約の仮登記がその後になされたという場合は、譲渡特約実行後も抵当権による競売があり得る形になります。
-
借地権設定期間中に契約の解約又は解除となった場合、建物取り壊しの上で更地返還を求める規約とするが、A社が抵当権を設定していてその返済が済んでいない状態だとどうなるでしょうか?
-
借地権設定期間中の解約又は解除ですが、金融機関に対して抵当権を設定している以上、期間内の解約または借地契約の合意解除は抵当権者に対して対抗することができないものとされています。これに対し、借地人の地代不払い等の債務不履行を理由とする解除の場合は、契約が解除されれば賃貸人からの建物収去土地明渡し請求が認容されますので、建物収去時に抵当権は消滅することになります。
-
借地権設定期間中に、A社の申立により土地の賃借権の譲渡を承諾する場合、当初にA社と締結した契約条項等は、第三者が引き継ぐ義務を有するものとなるでしょうか?それとも新たにその第三者と借地権の内容について協議して、契約条項等は設定し直すものとなるでしょうか?
-
借地権設定期間中に借地権が譲渡された場合には、借地契約の内容は同一性を保ったまま、譲受人に承継されることになります。
第6回(2009.01)
借主がフランチャイズの飲食店を開いているが、地代が滞ってきた。
契約書には解除の条項として、賃料の支払いが3ヶ月以上滞ったときと明記されている。
念の為、未払い4ヶ月目を待って書面で最後通告をしたが、誠意がないので契約解除を実行に移したい。
-
具体的にどのような手順を踏めばよい?
最後通告の段階において、借主がまだ通常どおり店を営業している場合と、既に店は休業しているが什器などがそのままの場合とでは、地主の契約解除の手順に違いはあるか?
-
-
地代の3ヶ月の不払を理由とする解除の可否
御質問は、地代の支払いが3ヶ月以上滞ったときの借地契約の解除の手順についてのものですが、前提として、借家契約の場合には家賃の3ヶ月分程度の滞納があれば背信性が認められ、借家契約を解除することが認められていますが、借地契約の場合には最低でも6ヶ月ないし1年程度の不払がなければ背信性が認められないのが一般的です。理由は、借地権は、借家権に比べて経済的価値が相当に高額であること、家賃の3ヶ月分に比べて、地代の3ヶ月分はさしたる金額ではないことなどがあげられます。
- 仮に1年程度の地代の滞納があった場合の解除の手順
契約の解除の手順は、まず配達証明付内容証明郵便で、未払地代を相当期間内(1週間~10日程度)に支払うよう催告し、催告期間内に滞納地代が支払われない場合には改めて通知することなく契約を解除しますという内容を通知することから始まります。
この解除通知が相手方に到達(これにより、法的には契約解除の効力が生じます。)してから、相手方と立ち退きの交渉を始めます。
-
この場合に、最後通告の段階で、借主が未だ店舗を通常とおり営業している場合には、一般的には任意に明け渡すケースは極めて少ないのです。この場合には、ある程度の任意交渉をした後、それでも埒があかない場合には、直ちに法的手続きを取る方が早い場合が多いと思います。建物収去土地明渡請求訴訟を裁判所に提起することになります。
- 相手方が既に休業状態で什器類がそのままの場合は、まず相手方の所在が判っている場合には、相手方に任意に何と何を持ち出したいのか確認し、残置するものについては賃貸人側で処分するので残置物の所有権放棄書に相手方の署名押印をもらいます。その場合の処分費用の負担を合意することになりますが、殆どのケースは賃貸人が事実上負担することになります (それでも、地代が入らないまま、放置されるよりは経済的な負担が少なくて済むという考え方だと思います。) 。
-
借主のフランチャイズ本部・借入銀行・什器のリース会社と話し合いをすべきか?
-
まずリース会社に連絡すると、リース物件を引き取りたいという場合が殆どですが、これで賃貸人側が撤去作業を行う手間が省けますので、リース会社には連絡をすべきものと思います。 フランチャイズに連絡して、未払地代を肩代わりしてくれるのであれば、有難いのですが、そうしたケースは決して多くないと思います。法的には賃借人に連絡すれば足りることですので、フランチャイズへの連絡は、そのときの状況に応じて判断されれば、どちらでも構わないものと思います。
-
店舗の解体整地を借主がしなかった場合、保証金を解体整地に充ててよいか?
保証金残金はどのようにすべきか?
-
保証金は、未払地代や原状回復費用に充当することができます。ですから、契約書で契約終了後の解体整地が借地人の義務と定められている以上は、それらを差し引いて構いません。全ての処理を終えた後の保証金残金は借地人に返還することになります。借地人の所在が判らない場合には、借地人の最後の住所地を管轄する法務局に供託しておくことになります。
第7回(2009.02)
-
下記事例の場合、「事業用定期借地権」の適用が可能か否か教えてください。
自己所有地に賃貸マンション(1階に店舗兼事務所、2階以上が居住用)を建設し、自己所有地に隣接した他人が所有する土地に上記賃貸マンションの「店舗兼事務所用」駐車場として賃借する場合、この他人所有地を「事業用定期借地権」を適用して契約を締結することは可能でしょうか?
-
-
借地借家法第23条が事業用定期借地権ですが、大原則があります。それは、専ら事業の用に供する『建物の所有』を目的としていることです。このため、駐車場は、青空駐車場的なものは建物がないため、『建物の所有』を目的としたものとはいえず、事業用定期借地権の対象とすることができません。青空駐車場のための土地の賃貸借は、民法上の土地賃貸借であって、借地借家法の対象とはされていないことに御注意下さい。
- 上記のように、隣地を駐車場としてのみ賃借する場合には定期借地権が設定できませんが、それでは、自己所有地に建設する賃貸マンションが隣地にもまたがって建設され、隣地には賃貸マンション部分と駐車場部分の両方が存在する場合には『建物の所有』の目的が満たされるので事業用定期借地権の設定が可能になるかというと、そうではありません。御相談の多くの方が勘違いをされておりますが、事業用定期借地権の対象となる建物は、事業の用に供する建物で、かつ、居住の用に供するものを除くと記載されております。賃貸マンションは、事業用ではあるのですが、居住用でもあるため、事業用定期借地権の成立要件を満たさないのです。
よって、今回のご相談の内容で定借を利用したいと考えた場合は、残り2つの定期借地権(一般定期借地権または建物譲渡特約付借地権)を利用するしかございません。ただし、残り2つの定期借地権も、『建物の所有』を目的としていますので、隣地を駐車場としてしか利用しない場合には、隣地の土地賃貸借契約は建物の所有を目的としないものとして、そもそも借地権の成立が認められない可能性があるので、どうしても隣地を駐車場として利用したい場合は、両方の土地に建物が跨がらないと問題がおきます。
これに対して、賃貸マンションも他人の所有地を借地して建築する場合、たとえばA氏が所有するA土地を賃貸マンション用地として賃借し、隣接するB氏が所有するB土地を賃貸マンションの駐車場として賃借する場合は、A土地とB土地とを一体として建物所有の目的で賃借していると見ることが可能です。
しかし、本件の場合は、借地するのは隣接地のみで、その土地には建物を建築しないとなると、借地の目的が「建物の所有」であると見ることが困難です。このため、定期借地権はおろか、そもそも『借地権』の成立要件を満たしていないと判断される可能性が高いということになります。
第8回(2009.03)
「事業用定期借地権における解約の可否」についていくつか質問します。
-
契約当初、中途解約の条項を入れていない場合、事業縮小の必要等を理由に中途解約を求めることはできますか?
-
法的には、定期借地権は「期間を定めた契約」(民法第618条)ですので、契約期間内における中途解約権の留保(いわゆる「期間内解約条項」「中途解約条項」)が規定されていない限り、解約権は認められておりません(民法第617条の反対解釈)。
したがって、法的には、賃貸人の同意を得ずに一方的に中途解約することは認められておらず、賃貸人から解約についての同意を得た上での合意による合意解約しかすることができません。
-
出来るとすれば、最低何ヶ月前に地主に相談すればよいですか?
-
一方的な中途解約権の行使はできませんが、合意解約の申込をすることは可能です(賃貸人がこれに応じてくれるか否かは別問題ですが)。解約申入期間については、民法上は土地の賃貸借は1年とされています(民法第617条)。
しかし、この規定は強行規定ではありませんので、実務の世界では、これを自由に修正して使っています。多いのは6ヶ月とするものと、1年とするものだと思います。
-
ペナルティがあるとすれば、どのようなものが考えられますか?
-
中途解約のペナルティとして最も問題となるのが、残存期間の賃料分を違約金として支払えとするものです。これは中途解約条項がある場合に、中途解約した場合には残存期間賃料を違約金として支払うというものですが、これは公序良俗違反として無効であるとするのが判例です。理由は、中途解約した場合には次の賃借人との契約が締結できるまでの相当期間程度の賃料分が違約金として相当であるとするもので、相当期間とは6ヶ月~1年程度とされています。したがって、通常は最大で1年程度の賃料相当額を違約金として支払えば解約が認められるべきであるということになります。今回もそれを目処に交渉されては如何かと思います。
ただし、今回のケースは、もともと中途解約権がないのですから、賃貸人側が1年程度の違約金であれば解約は認めないと言えば、解約ができないだけに終わってしまいます。1年を基準として、柔軟に対処されたほうがよいと思われます。
-
万一、公正証書を紛失していた場合、どのようにすればきれいに借地権の終了が出来ますか?
-
当事者間で解約合意書を作成すれば可能です。解約合意書には、事業用借地権を合意解約すること、解約の日付、その場合の精算条項(違約金等)の内容、当事者間で締結した事業用借地権設定契約公正証書は解約日以降は効力を喪失すること等を規定しておかれれば十分かと思います。
第9回(2009.04)
「建物譲渡特約付借地権の譲渡」について
<背景>5年前にA建築会社に30年の建物譲渡特約付借地権で土地を貸し、A建築会社は賃貸マンションを建てた。マンション自体はいつも満室で順調であったが、リーマンショック後、会社の資金繰りが悪くなり、3月に民事再生の適用を受けた。
-
A建築会社が資金回収のため、マンションを売却しようとしている。かなり安い価格を提示し、積極的に購入を勧めてきた。入居状況については今後も問題なさそうなので真剣に購入を検討しているが、
-
建物を購入した場合、A建築会社との土地の契約はどのように考えておけばよいか?
- 地主として気をつけておかなければならない問題はあるか?
-
-
譲渡特約付借地権上のマンションの譲渡
現在の法律関係は、土地の所有者が御質問者、A社が御質問者の土地につき建物譲渡特約付借地権を設定し、同借地上にA社所有のマンションが建築されているということになります。
この度、A社から上記マンションの購入を勧められているとのことですが、御質問者が借地上マンションを購入するということは、マンションとその敷地利用権である建物譲渡特約付借地権を一緒に購入することになります。
その結果、底地の所有者は御質問者、建物譲渡特約付借地権も御質問者、借地上建物も御質問者が有することとなりますので、賃貸人も賃借人も同一人となりますから、混同の法理により、建物譲渡特約付借地権は消滅し、御質問者が自己の所有する土地に自己の所有するマンションを所有しているということになります。
ただし、混同の法理には例外があります。マンションに抵当権が設定されている場合には、この抵当権の効力は借地権にも及びますので、マンションの抵当権が存続するのであれば、建物譲渡特約付借地権は消滅しないで残存することになります。しかし、通常はマンションの抵当権は抹消した上で売買されますので、この点は実務的には考慮する必要はないと思います。
- 留意すべき点
上記の場合に最も留意すべき点は、購入価格です。建物譲渡特約付借地権は、建物を相当の価格で購入することが予定されており、その場合にはいわゆる借地権価格で土地を引き取ることは予定されていません(つまり、借地権については通常の対価を支払うことなく消滅することになりますので、定期借地権の類型に数えられています。)。しかし、それは借地契約後30年以上経過した日にマンションを購入する場合であって、未だ5年しか経過していない場合には、通常の借地権付建物売買となります。
したがって、今回の売買は、譲渡特約付借地権の「譲渡特約」に基づく売買ではなく、譲渡特約付借地権とマンションの売買契約ですので、マンションの価格に5年を経過した建物譲渡特約付借地権の価格で買い取ることになります。この点に御留意下さい。
第10回(2009.05)
「定期借地権設定契約の当事者の変更」について
<背景>定期借地権制度がスタートした頃に、地主のAから子会社Bが定期借地権で土地を借り自社ビルを建てた。
-
CはBの親会社である。最近子会社Bが清算したため建物を引き継いだ。話によると、地主のAも数年前に亡くなり、現在は長男Dが相続しているという。
30年以上も契約期間が残存している中、地主・借地人双方とも担当が契約当時の者ではないため、今後の事を思うと不便を感じてきた。公正証書や当時の契約書は双方ともきちんと保管している。
-
新地主Dと新借地人Cはこの際、何か書類を交わしておこうと思っているが、表題・内容はどのように記せばよいか?
-
再度、公正証書を取り交わす必要はあるか?
-
子会社Bは契約当時、保証金返還請求権を保全する抵当権を設定していたが、現在は抹消してある。新借地人Cの名前で再度抵当権を設定したいが問題はあるか?新地主Dの許可はいるか?
-
-
定期借地権設定契約の当事者の変更
- 地主の相続による賃貸人の変更
本件では、定期借地契約の当事者が、地主の側も、借地人の側も変更されているとのことですが、まず、地主の変更は相続によるものですので、包括承継(法律上当然の地位承継)であり、御長男のDが遺産分割協議により定期借地契約を締結している土地を相続しているのであれば、借地契約の当事者変更をしなくとも、当然に賃貸人の地位が変更となっています。したがって、法的には、格別の契約行為はしなくとも、賃貸人がDであることに変わりはありません。
- 賃借人企業の変更
これに対し、子会社が清算したことから、親会社のC社が賃借人の地位を引き継いだということですが、これは借地権の特定承継 (法律上当然の承継ではなく個別の譲渡契約に基づいて地位を承継するもの) ですので、借地権の譲渡契約が締結されていることと、賃借権の場合にはこれに対する地主の承諾が要件となっています。賃借権の場合には、地主の承諾を得ていなければ、借地契約を解除されてしまいます。
それらの手続きがきちんと履践されているのであれば、法的には既に賃借人の地位はC社に変更されていますので、やはり、格別の契約行為をしなくとも、賃借人がCであることに変わりはありません。
- 新たな当事者間の契約締結
法的には上記のとおりですが、現在の賃貸人と賃借人との間で権利関係を確認しておくことは、今後の権利関係に対する誤解を防止する上でも好ましいことです。
この場合には、一般定期借地権設定契約確認書を取り交わすことになります。内容的には、契約書の前文で、「賃貸人Aと借地人B社との間で平成○年○月○日付で締結した一般定期借地権設定契約について、相続によりAの地位をDが承継し、B社の借地権を平成○年○月○日付譲渡契約によりC社が承継したことに伴い、新賃貸人Dと新借地人C社とが承継した一般定期借地権設定契約の内容が下記の約定であることを確認する。」という趣旨を確認することになるものと思います。
- 本件で検討しておくべき事項
なお、C社がB社から借地権を承継したとは書かれているものの、保証金返還請求権を保全するB社の抵当権は現在抹消されていると書かれています。この点からすると、B社の借地権を、C社が適正に引き継いでいるのかが明確ではないように思います。
何故なら、B社の借地権をC社が譲渡を受けて承継する場合は、保証金返還請求権もC社が債権譲渡を受け、これに伴い抵当権者の名義もC社に変更されているはずだからです。この手続きがなされていないだけではなく、抵当権が抹消されているということは、どのような手続でC社がB社の借地権を承継したのか、やや不明朗に思われます。
したがって、これらの経緯を確認した上で、新賃貸人となるDとの間で、借地契約の内容を確認しておくことが必要だと思います。
- 公正証書の要否
上記の確認書ですが、これをわざわざ公正証書にすることまでは必要ないと思います。
- 再度の抵当権設定
保証金返還請求権についての再度の抵当権設定をしたいとのことですが、B社が清算した際に、抵当権が抹消されているとなると、B社清算の際に保証金返還請求権はどのように処理されたかが疑問です。
抵当権が抹消されたということは、通常は保証金の返還がなされている場合ですので、保証金返還請求権がどのように処理されているかを確認しておく必要があります。もし、保証金返還請求権がB社からC社に譲渡されているというのであればその契約書が存在するか否かを確認して下さい。
譲渡を受けているのであれば、C社は賃貸人Dに対して保証金返還請求権を有していることになります。ただし、抵当権の設定は新たに賃貸人Dと締結することになりますので、Dがこれに応じない限り抵当権は設定することができません。
第11回(2009.06)
-
事業用定期借地権の締結にあたって地主からの質問です。
-
覚書から公正証書作成までの移行期間中に、相手方より「契約をやめる」と言われた場合、何ら拘束力はないのか?
-
覚書締結の時点で普通借地権は成立していると解釈できるか?
-
上記2の段階で土地賃貸借自体は成立するとすれば覚書締結の段階で仲介手数料支払義務は発生するのか?
-
-
事業用定期借地権設定のための覚書は、事業用定期借地権は公正証書によらなければ有効ではなく、かつ、これを私製の契約証書で合意すると普通借地権が成立してしまうため、「覚書」の形式で合意することとしています。
したがって、覚書は、今後、公証役場において、公証人に委嘱して事業用定期借地権の設定契約を締結する旨のスケジュールを合意するものですので、覚書それ自体は契約としての拘束力を持つものではありません。
ただし、相手方が契約をやめたいと言った場合に、ペナルティがあるか否かは覚書の中にペナルティ条項を盛り込んでいるか否かにより決まります。すなわち、覚書それ自体は借地契約としての拘束力を持つことはありませんが、覚書の中で、「何時までに公正証書の作成に応じなかった場合は違約金として金○○円を支払わなければならない」との趣旨を合意しておくことは可能です。
- 回答1で説明したとおり、覚書は借地契約を締結する意思表示ではありません。将来、契約を締結することを合意したものです。したがって、覚書締結の時点では、普通借地も定期借地もいずれも成立するものではありません。
- 覚書締結の時点では借地契約は成立していませんので、この段階では法的には仲介手数料支払義務は発生していません。
第12回(2009.07)
-
建物譲渡特約付借地権に関して
-
30年後の定期借家契約を事前に締結していない場合には普通借家契約が成立し、入居者の立退料などが発生するのでしょうか?
-
契約締結後、賃借人から途中解約を申入れされた場合、解約に応じざるを得ないのか?
-
契約時に譲渡価格を決める場合、どのように価格を決めたらよいのか。譲渡価格を0円とした場合には問題があるか?
-
-
御質問の趣旨は、30年後に譲渡特約を実行して借地上の建物の所有権を賃貸人が取得し、借地権が消滅した場合に、建物の賃借人から建物の使用の継続を請求された場合に、30年後のその借家人が定期借家契約ではなく普通借家契約を締結している借家人だった場合には、その明渡しを求めるには立退料が必要となるのかという御趣旨かと思います。
普通借家契約を締結している借家人は、譲渡特約実行後も普通借家契約の借家人となり、その明渡しを求めるには原則として立退料が必要となります。
- 期間を定めた契約の場合(譲渡特約付借地権は30年以上の期間を定めますので、期間を定めた契約に該当します。)、契約に中途解約権を定めていない限り、借地人は中途解約が出来ません(民法第618条)。契約書次第であるとお考え下さい。
- 譲渡価格は、30年後の「相当な対価」を決めるのですから不確定要素が多く迷われることが多いと思います。相当な対価の合意については、対価の算出方法ないし基準を合意する方法と、具体的な対価を合意する方法とがあります。
前者の対価の算出方法ないし基準を合意する方法とは、例えば、「30年後に賃貸人の指定する不動産鑑定士の鑑定価格による」とするもの、具体的な対価を合意する方法としては、具体的には金○○○○円と決める方法で、その基準は建物価格の○○%という形で決めるものが多いようです。
ただし、譲渡価格を「0」とすることは建物譲渡特約付借地権の要件を満たさなくなってしまいますので御注意下さい。何故なら、建物譲渡特約付借地権は「相当の対価」を支払うことが成立要件ですので、「0」では相当の対価を支払ったことになりません。
ここで対価については「正当の対価」とは規定されず、「相当の対価」と規定されていることに注意する必要があります。建物譲渡特約付借地権は「正当な対価」を要求していませんので、その時点における時価で買い取ることは求められてはいないのです。あくまで「相当の対価」であればよいのですから、建物建築価格の○○%ということは許容の範囲と考えられます。
第13回(2009.08)
賃貸事業が飽和状態または経営的に成り立たない場所での新たな土地有効活用が見直されています。ハウスメーカー・コンサルティング会社・建築会社などは介護運営会社とタイアップして超高齢社会が求める新たな土地有効活用の企画提案を、地元地域の医療・介護サービスへの社会貢献や名誉などに興味を示す地主に対して売り込みをかけております。しかし、商談において、借地50年という期間がネックとなるため、いわゆる『事業用定期借地権』を利用しての企画を持ち込もうと考えます。
-
1階をデイサービス、2階をショートステイなどの事業を行う場合、『事業用定期借地権』を利用することはできますか?
-
事業用定期借地権は、<1>借地上の建物が事業用であることと、<2>居住の用に供するものではないこと、が条件となります。
御質問の場合は、事業用であることは明らかですので、デイサービスやショートステイ施設が住居とみなされるかということが問題となります。「住居」とは人が日常的に起居する建物を指すといってよいと思われます。
かかる観点からみると、デイサービスは一日単位のサービスですから「住居」とみなされる余地はないものと思います。
また、ショートステイは、何日か人が寝起きすることは事実ですが、あくまで一時的な寝起きであって、日常的に起居するものとは言えませんので、やはり「住居」には該当しないと考えてよいと思います。その意味ではホテルと類似の施設と考えてよいといえます。
-
認知症対応型共同生活介護事業介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する「認知症対応型共同生活介護事業」等のための『グループホーム』を建てる場合も事業用定期借地権を利用できますか?
-
認知症対応型共同生活介護とは、認知症(痴呆)の状態にある要介護者等に対して、その共同生活を行なう住居(施設)内において行なう入浴・排せつ・食事等の介護・日常生活上の世話・機能訓練を指すものと考えられています。
そのためのグループホームは、主治医から認知症の診断を受けた利用者が、衣食住の費用を全額自己負担し、介護サービスに対してのみ1割自己負担(定額制)の介護保険を利用する完全個室制共同生活住居と考えられています。
これらの事業の目的と実態からすると、グループホームは、実際にそこで生活する利用者の観点からすると、利用者が日常的に生活する場そのものであって、まさに人が日常的に起居する住居と言わざるを得ないのではないかと思います。
したがって、少なくとも事業用定期借地権の解釈においては、御質問のグループホームは「住居」に該当し、事業用定期借地権の活用は困難ではないかと考えます。
第14回(2009.09)
「賃貸マンション事業と定期借地権活用の可否」について
-
築30年の賃貸マンション(土地・建物とも地主所有)に対して、借地権を設定し、地上権(法人1社にて設定)と底地権を分離したいのですが、対応年数等から考え20年の地上権設定契約が妥当と考えます。
居住用であるため事業用定借(20年)の設定はできませんので一般定借か普通借地権で話を進めようと考えております。
但し、契約書上は「20年間の借地契約とし、期間満了時に更地返還する」といった契約形態を取りたいのですが、この場合法的には意味のない期間設定ですが、地上権者側の意思提示という意味合いと地主に対して多少なりとも安心して頂きたくための苦肉の策としてこの方針で進めて行きたいのですが、何か問題点等はございますか?
-
-
賃貸マンションを一般定期借地権又は普通借地権で事業化する際の問題点
賃貸マンションという居住用借地契約であるため、利用できる類型は、<1>一般定期借地権か、<2>建物譲渡特約付借地権か、<3>普通借地権かのいずれかということになります。
事業者の方も、その点は御理解の上で、法的には無効であるとしても、当事者間で「20年の借地期間とし、期間満了時に更地返還する。」との契約としたいとの御考えのようですが、この考え方には以下の問題点があります。
1つは、一般定期借地権設定契約あるいは普通借地権設定契約において「20年の借地期間とし、期間満了時に更地返還する。」との特約が法的には無効であるとしても、その特約は紳士協定であるから、当事者が特約を守ってくれればラッキーであるし、仮にそれが守られず通用しなかったとしても、法的なあるべき姿に戻るだけのことであるから、いわば駄目元の精神で契約することは許されないのかという点です。この点については、注意すべき問題がいくつかあります。
- 一般定期借地権設定契約において特約を設けた場合
御高承のとおり、一般定期借地権設定契約は契約期間50年以上でなければ有効には設定できません。一般定期借地権設定契約において、契約期間を20年と定めた場合、一般定期借地権設定契約としては効力を生じません。この場合に、契約が全て無効であればともかくとして、一般定期借地権設定契約としては無効であるが、普通借地権設定契約としては有効と判断されることになります。
そうしますと、地主側は御社のアドバイスを受けて、特約により20年、仮に特約が守られなくとも一般定期借地契約により50年経てば借地契約は終了して土地が返還されると考えていた場合には、実際には御社のアドバイスにより普通借地権を成立させてしまったことになりますから、土地は戻って来ませんし、明渡しを求める場合には高額の立退料が必要となるということになります。
このような結果になった場合には、地主側から御社に対する損害賠償請求の問題が生じかねません。したがって、このような特約を一般定期借地権設定契約に盛り込むことは極めてリスクが大きいと判断せざるを得ません。
- 普通借地権設定契約に契約期間を20年と定めた場合とする旨の特約を定めた場合
20年の期間の定めは借地借家法の強行規定違反ですから無効となり、期間を定めなかった契約とみなされることになります。その結果、借地借家法に従い、期間30年間の普通借地権設定契約が成立したことになります。この場合も借地人が20年間の特約を遵守して土地を明け渡す可能性は限り無くゼロに近いと思われます。
この場合は、特約が無効であっても、最初から法律を守って期間を30年とした場合と同じ結論になるのだから駄目元でやってみる価値はあるのではないかと考える方も、あるいはおられるかもしれません。
しかし、普通借地権設定契約となると、当然ながら、権利金を授受する慣行のある地域においては、権利金を授受しなかった場合には認定課税を受けることとなります。課税を回避するためには、借地契約時に権利金を賃貸人と賃借人との間で授受するか、いわゆる相当地代を支払わなければなりません。現在、そのような高額の権利金あるいは地代を払って借地権の分譲を受ける借地人がどれだけいるかは市場の動向及び当該土地の立地条件によることになりますし、権利金を徴収することなく借地契約を締結した後に、権利金についての認定課税を受けた場合には、事業採算が当初説明したものとは大幅に狂うことになります。
- 賃貸マンションを所有する目的での借地契約を活用した事業
- 上記のとおり、一般定期借地権設定契約あるいは普通借地権設定契約において、契約期間を20年間とする契約形態のリスクは極めて大きいと言わざるを得ません。
仮に、どうしてもそのような特約を盛り込むというのであれば、地主側に対して、この特約を盛り込んだ場合には法的には定期借地権は認められず、普通借地権が発生することになり、土地の明渡しを請求するのは事実上不可能な事態になり得ること、立ち退きが得られる場合でも高額の立退料を支払う必要が生ずることをきちんと書面にて説明し、地主からも書面にてその旨の説明を受け了承した旨の記名押印を受けておく必要があります。
- 同時に、これは法的には普通借地権設定契約となりますので、税法上も、権利金を授受する慣行のある地域内で権利金を授受することなく普通借地契約を締結したと評価される場合には、権利金に関する認定課税があり得ること、そうなれば事業採算が大幅に狂ってくることが想定されるため、その点についても事前に書面で説明し、地主からも書面で了承を得ておく必要があります。
しかし、そのような不安定な内容の事業提案であることをきちんと地主に説明した場合に、地主がこれに応じるか否かは疑問がありますし、こうした不安定な事業提案を行うことが適切であるか否かについては再度検討される必要があるように思われます。
第15回(2009.10)
<背景>一般定期借地権を利用して11年前に家を建てた借主からの相談です。
仕事の関係で住まいを売却し、他の地域に引っ越すが、転貸の意思は無い。
-
一般定期借地権設定契約書には「地主の書面による承諾を得て、第三者に本件借地権を譲渡し又は本件土地を転貸することが出来る。」と記載されているが、地主は承諾を拒否することはできますか。実例はありますか。
-
地主の承諾拒否について
地主が借地権の譲渡について拒否できるか否かは、法的には一般定期借地権が地上権として設定されているか、賃借権として設定されているかにより異なります。 民法第612条は、賃借権の譲渡については賃貸人の承諾を得なければならない旨を定めていますので、賃借権として設定されている一般定期借地権は民法第612条の規定により、地主の承諾を得なければなりません。 これに対し、地上権は、物権法定主義に従い、物権である地上権の内容は基本的には民法の定めに従います。物権は自由譲渡性がその本質ですので、地上権は地主の承諾が本来的には不要です。 御質問の一般定期借地権が賃借権として設定されたものであれば、地主は承諾を拒否することが法的に可能ですし、普通借地権においては実際に承諾を拒否しているケースがあります。
-
承諾を拒否された場合、借地人にはどのような対処の方法がありますか。
-
承諾を拒否された場合の借地人側の対処法
地主が借地権の譲渡に対する承諾を拒否した場合、借地人側は、借地権の譲受人が賃借権を取得しても地主に不利となるおそれがないにも係らず地主が借地権の譲渡を承諾しないときは、裁判所に対して、地主の承諾に代わる許可を求めることができます。この手続を「借地非訟(しゃくちひしょう)手続」といい、地主の承諾に代わる許可を「代諾許可(だいだくきょか) 」といいます。
裁判所は、借地権の譲受人が暴力団員であるとか、地代の支払能力がない等の地主に不利益を与えるおそれがない限り許可をしてくれますので、地主が承諾しない場合でも借地権を譲渡することは可能です。
-
承諾をしてもらう場合、金品の要求はありますか。一般的な相場はどの程度でしょう。
-
承諾を受ける場合の金銭的対価の有無
一般的に借地非訟手続においては、裁判所が地主の承諾に代わる許可をする場合には、裁判所は地主に対して譲渡承諾料を支払うことを条件として許可決定をします。その場合の譲渡承諾料ですが、借地権価格の10%程度とされています。借地権価格については、裁判所が鑑定委員(不動産鑑定士)に鑑定を命じて決定されています。
第16回(2009.11)
借地人に相続が発生した場合について質問します。
-
定期借地権設定契約書に、借地人に相続が発生した場合には、相続人は相手方に対して遅滞なく住所・氏名を連絡しなければならないと記載されているものが多いが、相続人が複数いる場合は、相続人全員の住所・氏名を連絡する必要がありますか。その際、遺産分割協議書は必要ですか。
-
相続人が複数いる場合の連絡の方法は、借地契約に規定されている場合には、契約書の定めに従います。相続人が複数いる場合について具体的に定めていない場合には、要するに死亡した借地人の相続人の連絡先と氏名が明らかになることが必要であるという趣旨ですから、相続人のうちの誰か1名が代表者として連絡すれば契約上の要請は、とりあえず満たしていると考えてよいと思います。
遺産分割協議書ですが、通常は未分割の状態で連絡することが多いと思われますので、未分割の状態であること、代表者の氏名と連絡先を通知し、遺産分割協議が成立し、借地権の相続人が確定した段階で連絡することを連絡すれば足りると思います。遺産分割協議書の提示はとりあえず、この段階では要件ではありません。
なお、遺産分割協議が既に成立しているのであれば、借地上の建物登記に借地上建物(及び借地権)を相続した相続人の名義で登記されることになりますので、その旨の登記簿謄本又は全部事項証明書を示せば足りることだと思います。
-
相続協議が調っていない場合はどうすればよいでしょうか。
-
相続後、地主に連絡する際には遺産分割協議が調っていない場合が殆どだと思われますが、その場合には、現在分割協議が未了であること、分割協議が成立するまでの間の地代の支払方法(相続人の代表者名で一括して振り込むか、各相続人が各々の法定相続分に従って支払いをするか等)を連絡することになります。但し、地代は、土地を使用収益させるという不可分的な給付の対価としての性質がありますので、地代の支払債務は「不可分債務」と考えられ、各相続人は実質的には地代の支払債務については、遺産分割協議が成立して、当該借地の相続人が確定するまでの間は、地代については実質的には連帯債務を負っているのと同様になります(つまり、各相続人は月額地代のうち、自己の法定相続分に対応する額だけ支払えば足りるということではなく、他の相続人が支払わなかった場合には、その分も含めて支払う義務が生じます。)。
-
将来、地主は保証金を返還するときは、相続持分に応じて各相続人に返還しなければならないのでしょうか。
-
将来、保証金を返還するときまでには、借地人の側で遺産分割協議の成立により、当該借地権の相続人が確定していることが多いと思われます。相続人が確定しているときは、当該相続人が保証金返還請求権も取得すると定められている場合が多いと思われますので、相続人が遺産分割協議書で定めた内容に従って保証金を返還することになります。したがって、地主側では、保証金返還時期が到来するまでの間は、必ずしも遺産分割協議書を確認する必要はないのですが、保証金を返還する際には、誰が保証金返還請求権を相続したかを遺産分割協議書により確認する必要があります。
保証金返還時期が到来しても、遺産分割協議が成立していないような場合には保証金返還請求権のような可分の金銭債権は、遺産分割協議により債権の帰属が決定されない限り、各相続人が法定相続分に従い、分割債権として確定的に取得するものとされています。従って、この場合には、各相続人の法定相続分に応じて保証金を返還することになります。
第17回(2010.01)
「建物譲渡特約付借地権の設定」について
土地活用の一環として定期借地権の活用提案をする場合において、法第24条の建物譲渡特約付借地権で検討する場合について気になる点がありますので、質問させていただきます。
法第24条では、借地権設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる(第1項)とされております。仮に、24条借地権の設定契約を行う場合には、大きく以下の二つのパターンが考えられると思います。
- 予め、借地権を設定した日から30年を経過した特定の日を買戻し日として指定する。
例えば「借地権設定者は借地人より、本件借地権設定後30年を経過した20XX年Y月Z日に、時価にて本件建物を買戻し、本件借地契約を終了させることができる。」等とする。
- 借地権の買い戻し予定日を特定しない。
例えば「借地権設定後30年を経過した時点で借地権設定者が建物を買戻すことで借地契約を終了させることができる」のみの規定とする。
-
個人的には、1の場合は、特定した日に万が一買戻しができない場合には、借地権を消滅させることができなくなるのではないかと思いますので、<2>に近い表現で借地契約を設定するほうが無難ではないかと考えますが、このような解釈で宜しいでしょうか?
-
譲渡特約付借地権における譲渡特約について
建物譲渡特約付借地権の譲渡の日としては、借地権設定後「30年以上経過した日」を定めることが必要ですが、「特定の日」を定めることは必ずしも要件とされているわけではありません。
譲渡特約の内容としては、<1>借地権設定後「30年以上経過した日」を譲渡契約の始期とする始期付(確定期限付)売買契約とする場合と、<2>借地権設定後30年以上経過した日以降に予約完結権を行使することができる売買予約契約とする場合、とがあり得ます。
- 始期付(確定期限付)売買契約の場合
譲渡特約の内容が始期付(確定期限付)売買契約の場合に、その確定期限に借地権設定者が譲渡代金を支払わない場合には、借地権者は建物譲渡特約を解除することができます。解除されると建物譲渡特約が消滅します。30年以上の普通借地権に建物譲渡特約を付していた場合には、それ以後は普通借地権のみが存続することになります。
- 売買予約契約の場合
譲渡特約が売買予約契約としてなされた場合は、予定された時期に予約完結権が行使されないまま、借地権の存続期間が満了したとすると、建物譲渡特約を付した借地権が普通借地権である場合は、借地借家法の既定に従い借地契約が更新されますが、特段の合意が存在していない限り、建物譲渡特約の効力は更新後の借地契約にも及ぶと解されています。したがって、その後も予約完結権の行使が可能です。
したがって、確定期限として特定の日を定めて始期付売買契約を締結した場合には、その特定の日に売買契約の決済ができなければ譲渡特約の効力は消滅するのに対し、売買予約の場合には特別の定めがない限り、30年以上経過した後も予約完結権を行使することが可能となりますので、資金調達に不安がある場合には譲渡特約を売買予約型とするほうが望ましいことになります。
-
仮に、上記2のパターンで契約を行った場合で、借地権設定後、地主が窮迫してしまい、借地権設定後30年経過時点では建物の買戻しを行うことができず、例えば100年後に子孫が買取ることとなった場合において、時価は異なるのでしょうか?(この場合、建物本来の価格は無視していただき、例えば100年経過時点で買い戻す場合には、場所的利益等が30年経過時点で買い戻す場合よりも高額で評価される可能性があるか否かについて、ご意見をお願いします。)
-
相当の対価について
当初、30年経過した時点で予約完結権を行使するとの想定のもとに相当の対価を決定したのに、予定とは異なり、その後何年かを経過した後に予約完結権を行使する場合に相当の対価の額が異なるかということですが、建物譲渡特約付借地権において要求されているのは「相当の対価」であり、「正当な対価」ではありません。したがって、基本的には譲渡特約について定めた「相当の対価」の額が通用するものと思われますが、経済情勢や貨幣価値が余りに変動している場合には、いわゆる「事情変更の原則」の適用される一場面として、対価の額を修正する必要がある場合があり得ます。
第18回(2010.02)
1.賃料の全額前払いを受けた場合の賃料増減額請求権の行使の可否
-
期間50年の22条借地権の設定に際し、借地権設定時に借地権設定者が借地権者から賃料のほぼ全額について前払いを受け、現実の賃料は公租公課相当分とする内容とすることを検討しております。なお、賃料に関しては、「借地権設定者・借地権者ともに賃料増減額請求権は行使しない」旨の特約を入れたいと思いますが、こうした特約を入れても、借地権者は賃料減額請求権の行使ができる旨の話を聞いたことがありますが、その通りなのでしょうか?個人的に借地借家法を読んだところ、賃料増減額請求権にかかる規定は法第11条ですが、この節の強行規定である第16条で対象となっている条項は第10条、第13条、第14条のみであるため、借地権者の賃料減額請求権も有効であるように考えているのですが、この点についてご教示ください。
-
借地借家法は、定期借地権の場合であっても、借地借家法第11条に定める賃料増減額請求権を排除できる旨の定めを置いておりません。したがって、賃料の全額前払いを受けた場合であっても、借地借家法第11条に定める賃料増減額請求権の規定の適用を排除することはできません。
借地借家法第11条に定める賃料増減額請求権が強行規定であるか否かについては、通常の強行規定であれば当該規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効とする旨の規定があるのに、借地借家法第11条に対しては係る規定が存在しておりません。しかし、借地借家法第11条1項には「契約の条件にかかわらず」と規定されていることから、当事者がどのような契約条件を定めたとしても賃料増減額請求権は行使できると解されており、借地借家法第11条はいわゆる「解釈上の強行規定」とされています。
2.前払い賃料と借地権設定者の破産手続開始決定
-
前払い賃料を借地人が支払い、定期借地権が設定された場合は、借賃について下記のような登記がされると人から聞いております。仮に、借地権設定後に借地権設定者が破産する事態が発生し、競売により競落した第三者が生じた場合には、借地人はこの登記をもって当該第三者に対しては50年分の賃料のうち月額25,000円相当の前払い賃料の支払いは対抗できると考えて問題ないと考えておりますが、宜しいでしょうか?
仮に上述のように、借地契約上賃料増減額請求権を行使しない旨の内容となっている場合でも、競売の際に当該内容が目録等において提示されていなかった場合には、当該第三者は、賃料増額請求権の行使ができるものと考えますが、賃料前払い型借地権の登記が適正に為されている場合、賃料にかかる賃借人のリスクはその程度と考えて宜しいでしょうか?
前払い賃料の登記事例
| 借貸 |
月額金 |
30,000円 |
| (内訳) |
月払い分 |
5,000円 |
| 前払い分 |
(月額)25,000円 |
| (前払い賃料総額15,000,000円) |
-
賃貸借契約において賃料の前払いをした場合において、賃貸人が破産手続開始決定を受けた場合の法律関係については、旧破産法第63条は、「賃貸人カ破産ノ宣告ヲ受ケタル場合ニ於テハ借賃ノ前払又ハ借賃ノ債権ノ処分ハ破産宣告ノ時ニ於ケル登記及ヒ次期ニ関スルモノヲ除クノ外之ヲ持テ破産債権者ニ対抗スルコトヲ得ズ」と定めており、前払地代は当期と次期 (月払賃料であれば2ヶ月分)以外は破産債権者に対抗できないものと定めていました。月額25,000円であれば50年分の前払地代は1,500万円となりますが、このうち5万円のみ前払いを対抗できるとするのが旧破産法の規定でした。したがって、登記をしているから当然に前払地代を対抗できるというものではありませんでした。
しかし、この旧破産法63条の制限は、平成17年1月施行の改正破産法により削除されておりますので、現行破産法のもとでは、前払地代は破産債権者に対して制限なく対抗できることになります。
賃貸人に民事再生手続開始決定がなされた場合も、旧民事再生法では旧破産法63条を準用していましたが、旧破産法63条の削除により、破産の場合と同様に前払地代を制限なく再生債権者に対抗することができます。
第19回(2010.05)
事業用借地権の契約が期間満了を迎えようとしている事業者からのご相談が増えつつあります。 そこで、地主側・借主側双方が再契約を希望している場合についてお尋ねします。
-
当初の契約期間が20年で、再契約も同期間で締結する場合は公正証書の作成は不要か? また、特約や条項の追加・修正等のみの場合も公正証書は不要か?
-
事業用借地権は、定期借地権ですので、契約期間の満了により契約は終了してしまいます。すなわち、再契約は、更新とは異なり、従前の契約は跡形もなく消滅しますので、これまで定期借地権を締結したことのない当事者が新規に定期借地権の契約をするのと全く同一となります。 したがって、期間が従前と同一であれ、条項を若干修正するだけの変更であれ、すべて新規に事業用定期借地権設定契約をする場合と同じ条件を満たさなければなりません。よって、いずれの場合も公正証書による契約が必要となります。
-
どのような内容で再契約を交わした場合に公正証書を作り直さなければならないのか?
-
全ての再契約について公正証書による必要があります。
-
再契約にあたり留意する点があればご教示ください。当初20年であったが契約期間を30年未満で交わす場合と、30年を超えて交わす場合とにわけてご説明いただけますでしょうか。
-
いずれも公正証書による必要がありますが、30年未満の期間を定めた事業用定期借地権の場合、これと同一の期間で設定される普通借地権はあり得ませんが、30年以上の期間で事業用定期借地権を設定する場合は、これと同一期間の普通借地権が存在することがあり得ます。 このため、平成20年1月1日施行の借地借家法の改正では、30年以上の期間を定める事業用定期借地権の場合は、30年以上の普通借地権との区別を明確にするため、事業用定期借地権であっても、一般定期借地権と同様に、3つの特約(1.更新しない、2.建物再築等による存続期間の延長をしない、3.法13条の建物買取請求権を行使しない) をしなければならないこととされています。 30年未満の事業用定期借地権であれば、事業用定期借地権の要件(専ら事業用の建物でかつ非居住用の建物の所有を目的とすること、契約期間が10年以上30年未満であること) を満たせば当然に事業用定期借地権としての効果が得られていましたが、30年以上の場合は上記3つの特約を交わしていない限り、事業用定期借地権としての効果が得られませんので、この点にご留意下さい。
第20回(2010.06)
「地主が所有する土地・建物のうち、土地のみを第三者に売却し、地主が買主から売却した土地について定期借地権の設定を受け、定期借地権に基づき建物をそのまま保有し続け、期間満了後に建物を土地所有者が引き取る」とのスキームについてお尋ねいたします。
-
全ての定期借地権類型に当てはまるスキームか?
-
土地のみを売却し、売却した土地に定期借地権の設定を受けて、従前地主が建物を所有し続ける方式は、事業用ビル等における、いわゆるセールス・アンド・リースバックの土地版のようなものですが、このスキームで建物を無償で移転する方式に理論的に当てはまり得るのは一般定期借地権と事業用定期借地権です。契約終了時に無償で地主が建物を取得する特約が有効となるのは、この2つのみだからです。 建物譲渡特約付借地権は、定期借地権に譲渡特約を付している場合でない限り、期間が満了しても土地は返還されませんので、土地の返還を受けるには譲渡特約を実行するしかなく、「相当の対価」を授受して建物を取得することが要件となります。したがって、期間満了時に土地所有者が無償で建物を取得することができません。30年以上の期間満了時に土地所有者が相当の対価をもって建物を買い取るということであれば、建物譲渡特約付借地権でも理論的には可能だと思います。
-
このスキームに問題点があるとすれば何か?
-
このスキームは、法的には可能ですが、事業採算等、経済的に成り立つか否かが明確ではありません。土地を購入して旧地主に土地を定期借地権で貸す第三者にとって、土地の購入代金と、その後に受け取る地代収入とを比較した場合に、利回りとして充分であるのか等が気になるところです。条件にもよるとは思いますが、このような第三者 (B) が現れるだけの条件提示ができるか否かが問題になるものと思います。
-
このスキームが有効な場合、どのような場合に有利に機能するか?
-
このスキームは、土地を購入する第三者が出現するのであれば、旧地主の資金調達手段となりますし、地価が比較的高額な地域である場合には、旧地主の相続税対策になり得るかとは思います。
第21回(2010.07)
「一般住宅の定期借地権契約」について、状況を下記と仮定してお尋ねいたします。契約後12年が経過している中で、賃借人が地代を3ヶ月以上滞納し催告しても支払われておらず、その後、保証金に対しては質権設定の金融機関から地代の支払いを地主に対して申し入れがきています。
-
地主としては、契約書約定に基づき、地代延滞による契約の解除をし、更地にしてもいいか?
-
賃借人が地代を3ヶ月以上滞納し、賃貸人からは既に催告がなされているにもかかわらず支払いがない状態であれば、賃貸借契約書の内容にもよりますが、一応解除の要件を備えていると考えられます。 ところが、その後に保証金に質権を設定している金融機関から地代の代払いの申入れがあるとのことですので、借地人が金融機関から融資を受けているケースであると思われます。この場合には、金融機関が借地人に融資を実行するに当たり、賃貸人が金融機関に差し入れている書面があるか否かを確認しておく必要があります。金融機関によっては、借地人に融資を実行する際に、賃貸人・地主から借地上の建物に金融機関の担保権を設定することの承諾書を徴求するほか、借地人が地代を滞納した場合には、いきなり解除することなく、金融機関に通知し金融機関の地代の代払いの意向を確認することを義務付ける念書等を徴求することもあり得ます。
- 金融機関に対し、地代の滞納があった場合には金融機関に通知するとともに金融機関からの地代の代払いの申入れがあった場合にはこれを受ける旨の賃貸人・地主の念書等が提出されている場合 かかる念書がある場合に、これに反して解除を強行し、借地上の建物の解体がなされた場合には、賃貸人・地主は金融機関から損害賠償請求を受けることになります(金融機関が借地上建物に抵当権を設定している場合には、契約の解除、建物の解体により、金融機関の抵当権が消滅してしまいますので、金融機関の損害額は多額になり、地主に対する損害賠償請求額もかなりの多額になる可能性があります。)。
- 金融機関に対する念書が一切存在しない場合 この場合には、賃貸人・地主は解除の要件が発生すれば解除をすることが可能です。問題は、金融機関から地代の支払いを地主に対して申入れていることの中身です。何故なら、債務の弁済は、原則として、必ずしも債務者でなくとも、第三者でも有効に弁済することができるからです。したがって、金融機関が債務者である借地人に代わって第三者として地代支払債務を弁済すれば、「地代の滞納」という解除の要件が消滅してしまいます。 そして、債務の弁済に関しては、弁済を完了しなくとも、「弁済の提供」がなされれば、債務者は弁済提供の時から債務不履行によって生ずる一切の責任を免れるものとされています(民法第492条) 。 「弁済の提供」の方法としては、民法は、1.現実の提供と、2.口頭の提供の2種類を認めています。「現実の提供」とは、債務の内容が地代支払債務であるときは、支払うべき地代額全額を現実に債務の支払場所に持参して、債権者に実際に提供することをいいます。仮に、金融機関から地代の代払いの申入れの意味が、金融機関が未払地代額等全額を持参して地主宅を訪問し地主に未払地代額相当の金銭を提供したということであれば、その時点で地代支払債務については現実の提供がなされており、債務不履行によって生ずる責任を免れることになりますので、契約の解除という債務不履行によって生ずる責任を追及できなくなる可能性があります。 また、「口頭の提供」とは、債権者が契約を解除する方針等で予め弁済の受領を拒んでいるときには、現実の提供が可能であっても、それをなさしめることは公平ではないため、債務者は、債権者が弁済に協力するのであれば弁済をなし得るだけの準備をしているということを債権者に通知して弁済の受領を求めることをいいます。地主側が地代は受け取る意思がないと述べているのに対し、金融機関が弁済の準備をしており、いつでも地主が受け入れるのであれば未払地代は金融機関が支払うとの通知がなされていたとすれば、やはり弁済の提供があったものと見られる可能性が高いと思われます。この場合にも契約の解除はできなくなります。 これに対し、地主側は受領拒絶の意思を表明していないのに、金融機関からただ単に支払いの意向があるとの連絡を受けただけの場合には、民法第492条に定める法的意味での「弁済の提供」があったとは言い難いと思われます。 しかし、金融機関から地代の代払いをする旨の意向の表明を受けているのにこれを無視して直ちに解除、建物収去のための手続きに入ることは、金融機関との間で損害賠償をめぐって無用の紛争を生じることになりかねません。金融機関との調整を行われたほうが無難であると思われます。
-
賃借人がいない為、保証金で建物を解体しても問題ないでしょうか?
-
借地人がいないため、保証金で建物を解体しても問題がないかということですが、仮に金融機関との関係も問題なく契約の解除が有効になされた場合、借地人が現地にいないとしても、借地上の建物は借地人が所有権を有していますので保証金をもって勝手に建物を解体することはできません。他人の建物を勝手に壊した場合には建造物損壊罪(5年以下の懲役)という刑法上の犯罪を犯したことになります。したがって、借地上建物の解体は、借地人の了解を得て行う必要があります。借地人の行方が知れず、了解が得られない場合には、裁判所に建物収去・土地明渡を求める裁判を提起し、建物収去の判決を得て、強制執行手続で行うのが本則です。
-
賃借人が現在入居していない場合、家具や家財の処分方法は?
-
賃借人が現在居住していない場合に、家具や家財道具の処理はどのようにするかという点ですが、家具や家財道具も前問の場合と同様に、借地人の所有物ですので、勝手にこれを処分すると器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金等) という刑法上の犯罪となります。したがって、家具や家財道具の処理は、借地人の了解を得て行う必要があります。借地人の行方が知れず、了解が得られない場合には、裁判所に建物収去・土地明渡を求めると同時に未払地代の支払いを求める裁判を提起し、未払地代を支払えとの判決を得て、動産競売の強制執行手続で行うのが本則です。
第22回(2010.08)
「定期借地上建物の競売手続に関する問題点」について、状況を下記と仮定してお尋ねいたします。
一般定期借地権(51年間)で、土地に建物所有者名義で賃借権設定登記を設定した契約だったが、建物所有者が建物建設費の融資返済を滞納したため、現在建物は競売中。ただし、地代については債権者から支払いを受けているため滞納はない。
-
現在の一般定期借地権(賃借権)設定契約書の借地権の譲渡等の条項に基づき競落人と現在の定期借地権を継続する場合、問題点はないか?
-
借地上建物の競売があっても、競落人との間で定期借地契約を継続される御意思がおありであれば、定期借地契約の存続自体については問題はありません。ただし、定期借地契約において保証金を授受しておられる場合には、競売実務との関係で問題を生ずることがあります。 保証金を授受している定期借地契約の場合は、借地権の譲渡においては、保証金返還請求権は借地権の譲受人に承継される旨の規定を設けて、借地権の譲渡があっても貸主は保証金を返還しなくともよいとのスキームを構築しています。 したがって、競売で借地権が移動した場合も、旧借地人も買受人(借地権の譲受人)もこの規定を遵守して、その通りに処理されれば問題はないのですが、旧借地人が保証金についても金融機関からの融資を受けており、保証金返還請求権に質権を設定しているケースがあります。このケースでは、保証金返還請求権に質権を設定した金融機関 (ほとんどの場合、競売を申し立てた金融機関だと思われます。) は質権についても弁済期が到来したと主張して、貸主に対して保証金の支払いを求めてくるケースがあります。 競売手続においても、定期借地契約に定めた保証金返還請求権は買受人に承継されるとの規定が適用されるかという問題になるのですが、競売実務においては、特約がなければ一般には保証金は買受人には承継されないとの判断がなされており、かかる特約がある場合も競売価格を決定する際には保証金は買受人には承継されないとの前提で価格を決めている場合もあるようです。 この場合には、保証金返還請求権が買受人に承継されないとすると、保証金返還請求権は旧借地人が有したままとなります。この場合には、旧借地人は定期借地契約関係から離脱するため、保証金返還請求権は弁済期が到来することと解されることになります。 そこで、旧借地人が保証金についても金融機関からの融資を受けて、保証金返還請求権に質権を設定している場合には、保証金に質権を有する金融機関から貸主に対して保証金の返還を求められる場合があり得ることになります。 もっとも、その場合でも、買受人は当然に借地権を取得するわけではなく、借地権が賃借権である場合には、民法612条により、貸主の承諾を得ない限り、買受人は借地権を有効に取得することは出来ません。この貸主の承諾を求める手続きの過程で、貸主としては、買受人が新たに保証金を差し入れなければ借地権の譲渡を承諾しないとの意思を表明して、保証金を新たに獲得することは可能かと思います。しかし、その場合でも、当初の定期借地権設定時の保証金の額と、現時点での保証金の額との差額につき、マイナスを生じるという問題点はあり得るものと思います。また、借地権が地上権である場合には、この手法は用いることが出来ません。 この点が、競売手続における問題点になるものと思われます。
-
土地に登記されている賃借権設定登記権利者の名義人変更にあたり、現在の登記名義人の協力が得られない場合どうしたらよいのか?
-
競売手続の場合には、買受人が代金を納付したときは、裁判所書記官は、買受人の取得した権利の移転の登記を嘱託しなければならないとされています(民事執行法第82条1項)。
第23回(2010.09)
地主Aと借主Bとの期間10年の事業用借地権が3カ月前に終了した。契約終了後に借主Bは引っ越ししたが、地主Aと借主Bは知人であったため、解体費が無いとのことで、借主B名義のまま空き家になっていた。借主Bは最近仕事仲間の友人Cを地主Aに紹介し、借主B名義の空き家をCに譲渡し、新たに地主Aと新借主Cと期間10年の事業用借地権を結ぶ段取りとなった。
-
契約期間満了後3か月ほど期間が過ぎているが、旧借主Bが自分名義の建物を友人Cに有償で譲渡することに問題はないか?
-
事業用借地権の期間満了から3ヶ月経過した時点では、旧借地人の所有する借地上建物は、土地利用権限(事業用借地権)を既に喪失しているため、土地を不法占拠している状態となっています。従って、通常であれば、旧借地人が借地上建物を第三者に譲渡することは問題がありますが(建物を第三者に譲渡すると、建物を譲り受けた第三者が土地の不法占拠者となり、地主から建物収去土地明渡請求を受ける立場になります。)、地主と新たに事業用定期借地権設定契約を締結する者に同建物を譲渡するということであれば、建物を所有する第三者は土地の利用権限である事業用定期借地権を有することになりますので問題はないと考えられます。 また、事業用借地権の期間満了から3ヶ月経過しているのですから、本来であれば同建物は解体撤去すべきものですが、貸主と旧借地人と第三者との間でこれを譲渡し、新たな事業用定期借地権の目的とすることに合意しているのであればその合意を否定しなければならない理由はありません。
-
新たに建物の所有になった友人Cは、その建物を利用して地主Aと期間10年の事業用借地権を結ぶことに問題はないか?
-
借地上建物の譲受人は、新たな建物の所有者となりますが、この建物を利用して事業用定期借地権を設定することには全く問題はありません。旧借地人との間の事業用借地権契約では期間の満了により取り壊すべきものですが、事業用借地権契約が終了していることは明らかですし、解体すべきであったものを、解体せずに新たな契約の目的とすることは関係当事者が合意していれば、これを否定する理由はありません。
-
上記2つの質問において問題が無い場合、空き家の譲渡契約の時期と、地主との10年の事業用借地権の公正証書を結ぶ時期とを同時にしないといけないのか?
-
建物の譲渡契約と事業用定期借地権の公正証書作成とは必ずしも同時に行う必要はありません。事業用定期借地権の公正証書を作成すれば(事業用定期借地権の公正証書は建物が存立していることが要件ではなく、事業用かつ非居住用建物の所有を『目的』として借地権設定の合意をすることです。)、その時点以降に建物の譲渡契約を締結すればよいことになります。ただし、事業用定期借地権の公正証書を作成する前に建物の譲渡契約を締結することは、万一、何らかの事情で事業用定期借地権公正証書が作成できない事態が生じたときには、問題を生じますので、事業用定期借地権公正証書と同時か、それ以降に建物譲渡契約を締結するのであれば問題はないと御考え下さい。
第24回(2010.10)
会社Aは、自社所有地を会社Bに事業用定期借地権で賃貸することを検討しているが、その敷地内に会社A名義の空き家が存在している。そして会社Bはその空き家も含めて賃貸したい意向がある。
-
契会社Aと会社Bとは、土地は事業用定期借地契約を、空き家は定期借家契約を締結することを検討しているが問題はないか?
-
会社Aが自社所有地を会社Bに事業用定期借地権で賃貸し、その敷地内に存する会社A名義の空き家をBに建物賃貸することは可能かということですが、問題点は、借地権は排他的な占有権を付与する契約だということです。 会社Aが会社Bに事業用定期借地権を設定すれば、会社Bは賃借した土地全体について排他的占有権を有しています。それにもかかわらず、会社Aが会社Bに同土地上に存する建物を賃貸するということは、会社Aは、会社Bが排他的占有権を有する土地上に建物を所有していることになります。この事実が、借地権が排他的占有権を付与する契約であることと相容れない事実となってしまいます。 このため、こうした形態を可能にするためには、会社Aが、自社所有地のうち空き家の敷地部分を除いた土地を会社Bに対して事業用定期借地権を設定し、空き家については、会社Aの所有で会社Bへの借地権が未だ設定されていない土地上に会社Aが所有している空き家を会社Bに賃貸する、という方法を取ります。
-
会社Bは、会社B名義の建物を空き家とは別に建築を検討しているが、契約条項に関して特約事項として明記すべき事項や注意する点はあるか?
-
会社Bが空き家とは別に会社B名義の建物の建築を予定しているということですが、仮に、会社Bが敷地全体について事業用定期借地権の設定を受けていることを前提に空き家を会社Bに賃貸するとすれば、空き家の敷地部分の土地については会社Bが自らの借地権に基づいて会社Aに賃貸し、会社Aが一種の転借地権に基づき所有する空き家を会社Bに賃貸するという特約を設けることになると思われますが、極めてテクニカルな特約であり、それであれば、上記1の方法によるほうが簡明かと思われます。
-
会社A名義の空き家が建っている敷地を当初から事業用定期借地の対象外とする方法もあるかと思うが、出来れば最初から対象地にしたい。もし、当初は除外し、後日会社Aが空き家を解体し、会社Bが会社B名義で新築する場合、事業用定期借地の途中の変更として、新たに賃貸の対象地として加えることは可能か?
-
当初は上記1の方法を取り、空き家の敷地部分を除いた土地に事業用定期借地権を設定し、後日、会社Aが空き家を解体した場合に、会社Bが、会社B名義で同部分に建物を新築する方法としては、空き家の敷地部分の土地に新たに事業用定期借地権を設定することになります。ただし、事業用定期借地権の期間は10年以上50年以下とされ、最短期間を10年以上とする制限がありますので、たとえば20年の事業用定期借地権が設定されている場合に、12年後に空き家が解体された場合、既に設定されている事業用定期借地権の残存期間は8年しかありませんが新たに事業用定期借地権を設定する以上は、10年間の事業用定期借地権を設定するほかありません。 これでは不都合を生じてしまいますので、新たに事業用定期借地権を設定するのではなく、既に存在する事業用定期借地権の借地範囲の追加変更という形で処理できないかという点が問題になると思います。定期借地権の内容変更の可否につき、事業用定期借地権の期間の延長は可能と考えられます。たとえば当初10年間の約定で事業用定期借地権を設定した後、契約期間を10年から12年に延長する合意ですが、契約成立時に発生した事業用定期借地権の内容は何ら変更がなく、ただ単に当初の期間を延長する旨の合意をするだけですから、延長後の期間が事業用定期借地権の長期制限 (50年未満) に抵触しない限り、かかる期間延長の合意は有効と考えてよいものと思われます。 これに対して、事業用定期借地権の借地権の対象範囲の変更は、契約成立時に発生した事業用定期借地権とは、借地権の及ぶ範囲自体が変わるものであり、借地権の設定される土地の面から見れば、それまで借地権の設定されていない土地に新たに借地権を設定することになりますので、期間延長の合意の場合とは異なり、その有効性については疑念をもたれることがあり、少なくとも、その有効性については見解が分かれるものと思われます。
第25回(2010.11)
定期借地物件の競売とその後の処理についてお尋ねいたします。
-
賃貸人Bと一般定期借地権設定契約を締結したAが、借地上建物取得時の住宅ローンの返済が不能となり、金融機関が借地上建物の競売を申立て、Cが借地上建物を競売手続により買い受けた場合、旧借地人A、賃貸人B、買受人Cの各人に何か問題が発生することはないか?
-
旧借地人Aの所有する借地上建物が競売され、競売手続により買受人Cに借地上の建物所有権が移転した場合、建物敷地である一般定期借地権も買受人Cが買受けたこととなりますので、買受人Cは、借地上の建物と一般定期借地権を取得したことになります。
- この場合、買受人Cは、裁判所の競売手続により裁判所の売却許可を受けて建物と借地権を取得していますが、借地権は旧借地人Aから買受人Cに譲渡されているのですから、買受人Cは、Aからの借地権譲渡につき、賃貸人であるBの承諾を得る必要があります。Cは裁判所の売却許可を得てはいますが、それは強制執行手続における売却許可であって、民法の借地契約法制にかかる借地権の譲渡についての賃貸人の承諾は別途に必要となるからです(民法第612条)。
- Cが、賃貸人Bの承諾を得ることなく借地を使用収益すると、賃貸人BはC が競売手続により承継した一般定期借地契約を解除することができますのでCは、まずBの承諾を求める必要があります。 Cへの借地権譲渡が賃貸人Bに格別の不利益をもたらすおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しないときは、買受人Cは、地方裁判所に賃貸人Bの承諾に代わる許可を求めることができます。この手続きを「借地非訟 (しゃくち ひしょう)手続といいます。 借地非訟手続が申し立てられた場合、Cへの借地権譲渡が賃貸人Bに格別の不利益を及ぼさず相当なものであるときは、裁判所は賃貸人Bの承諾に代わる許可決定をします。この場合の許可は無条件ではなく、賃貸人Bに対して譲渡承諾料を支払うことを条件として許可がなされることになります。賃貸人に支払うべき譲渡承諾料は、一応の目安として、借地権価格の10%相当額と考えておかれればよいと思います。
- ただし、借地非訟を申し立てた場合に、必ず裁判所の許可決定が出されるとは限りません。重要な点ですが、借地非訟が申し立てられた際に、賃貸人が、借地権を第三者に譲渡するくらいであれば、賃貸人Bが自ら借地権を買い取る旨を裁判所に申立てることができます。この場合には、賃貸人Bは「相当な価格」で借地権を買い取ることが可能です。これを賃貸人の「介入権」といいます。介入権が行使される事案はそれほど多いわけではありませんが、賃貸人Bが介入権を行使してきた場合には、Cは競売手続で取得した一般定期借地権を賃貸人に相当額で譲渡しなければならなくなりますので、この点に注意が必要です。
- Cへの借地権譲渡につき、賃貸人Bの承諾あるいは借地非訟手続における裁判所の許可が得られれば、旧借地人Aは、一般定期借地契約から離脱し、以後は賃貸人Bと新借地人Cとの間で一般定期借地契約が継続していくことになります。 なお、A・B間の一般定期借地権設定契約において、AからBに対して保証金が預託されていた場合ですが、現在の強制執行実務によれば、AがBに対して有していた保証金返還請求権は、当然にはCには承継されないものと扱われています。強制執行実務では、Cに借地権が移転するまでの間のAの賃料債務の不履行その他の債務を保証金から差し引き、保証金の残額はAに返還されることになります。したがって、AのBに対する保証金返還請求権に金融機関の質権が設定されているような場合には、賃貸人BはAから預託を受けていた保証金を、これに質権を設定していた金融機関に対して返済することになります。
-
賃貸人Bは新借地人Cと今後どのように対処すればよいか?
-
賃貸人Bとしては、まずは新借地人Cと面談のうえ、Cに対する借地権の譲渡を承諾するか否かを判断します。その際には、上記のとおり、保証金返還請求権がCには承継されないことから、Aから預託を受けた保証金はAないしAの債権者である金融機関等に返済するとともに、Cから新たな保証金その他の一時金を支払うよう交渉することになります。
第26回(2010.12)
平成6年に地主Bと建設業者Cとが定期借地権を結び、建売を計画したが、それを購入した者借主Aが2台目の車の車庫が必要になったので、庭の空地部分に借主Aの費用で駐車場(砂利を敷く程度)を作った。1年後に駐車場付近の土地が何らかの原因で陥没したが、特に借主Aは地主Bに報告することなく、陥没地を借主A負担で補修した。しかし、今年、同じ部分が大きく陥没し費用も大がかりになることが分かった。 このような状況における、賃借土地の地盤沈下した部分の補修費の負担についてお尋ねいたします。
-
賃借土地の地盤沈下した部分の補修費は誰が負担するべきか?
-
賃貸した土地の一部が地盤沈下した場合、補修義務を負うのは本来的には賃貸人Bです。何故なら、民法第609条は、賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負うものと規定しているからです。 本件では、借地の一部に駐車場を作ったのは借地人Aだということですが、Aの駐車場設置行為に問題があって地盤沈下がAの駐車場設置行為によって発生したものであればAが責任を負いますが、Aが設置した駐車場であっても、Aの駐車場設置行為とは関係なく発生した地盤沈下であれば、賃貸人Bが補修責任を負うことになります。
-
建設業者の責任はあるのか?
-
地盤沈下については、土地を造成した業者の造成工事に原因があるときは、当該造成工事業者にも責任があります。しかし、本件では地盤沈下の発生した場所は建設工事業者Cが造成した範囲ではないとのことですから、建設業者Cには原則として補修責任はないと考えてよいと思います。
-
建物の一部に陥没が生じた場合の措置は?
-
土地が地盤沈下した場合、賃貸対象物は土地ですから、土地の不具合については賃貸人に補修義務があります。しかし、建物に陥没が生じた場合には、建物は賃貸対象物ではなく、借地人Aの所有物ですので、Bに賃貸人としての補修義務があるわけではありません。法的には、建物が陥没したことについての損害賠償の問題となるものと考えられます。賃貸人Bは、建物陥没により借地人Aが被った損害を賠償すべきことになります。建設業者Cは、陥没した部分の造成工事を行ってはおりませんので、基本的には責任はないものと考えられます。 しかし、実際上の解決としては、賃貸人Bが地盤の補修を行う際に、併せて借地人A所有の建物についても必要な補修を施すことが好ましいと思われます。
-
土地全体を建設会社が造成し、建物には付随していない場所で陥没事故が起きた場合は、建設会社に責任はあるのか?
-
土地全体を建設会社が造成し、建物には付随していない駐車場敷地が陥没した場合、一度は地主が補修したものの、再度陥没事故が起こった場合、造成工事を行った建設会社は責任を負うかという問題ですが、ポイントは当該土地の陥没が、自然現象であるのか、造成工事に起因するものであるのかということです。 陥没事象が、造成工事には関係なく、自然現象であったとすれば、その補修費用等は地主が負担すべきもので、造成工事業者には責任はありません。他方において、当該陥没が造成工事の不具合等に起因していた場合、あるいは造成工事中に業者として当然認知すべき土地の不具合を見逃していたような場合であれば、造成工事業者に責任があることになります。 その点が、現場を調査して確認できるか否かがポイントとなります。今回の事例は、最初の陥没が引渡後約10年を経過して発生し、今回が2度目の陥没であるとのことですが、一般的には造成工事の不具合に起因しているのであれば、引渡後早期に陥没が発生するのではないかとの疑問があり、直ちに造成工事業者の責任であるとも断じ難い側面があるように思われます。自然現象による陥没があり得る地域であるのかも含めて、現場調査の結果により、結論が異なるものと思われます。
-
今年陥没事故が起こったが、造成工事が平成6年頃であり工事から16年経過しているが、現時点でも責任はあるのか?時効はあるのか?
-
民法では、請負契約における瑕疵担保責任の期間については、「土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵については引渡しの後5年間その担保の責任を負う。だだし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。」 (民法638条) と定めています。 本件では、引渡後16年を経過して、初めて建設工事業者に通知があったとのことですので、法的には瑕疵担保期間は経過しているものと思われます。ただし、造成工事に不具合があった場合は、瑕疵担保責任ではなく、不完全な造成工事をしたことが不法行為であると主張してくるケースは少なくありません。不法行為の時効は、被害者が損害を知った時から3年間、行為の時から20年とされていますので、瑕疵担保期間を経過している場合は不法行為を主張するということがよく行われていますので、この点に御留意下さい。
第27回(2011.01)
「コンビニ会社に対する事業用定期借地権の設定」に関してお尋ねいたします。
-
「借地権の譲渡については地主の承諾を得るとの文言がなく、期限が来ると必ず土地が戻ってくるし、賃料も必ず入ってくる。」との意見や事業用定期借地権の登記の要否等については、地主側から見てどのように評価できるか?
-
- まず「借地権の譲渡については地主の承諾を得る」との文言がないとのことですが、設定する事業用定期借地権が地上権なのか賃借権なのかにより結論が異なります。地上権であれば、もともと地上権の第三者に対する譲渡は自由に行うことができますので、契約において「地主の承諾を要する」との特約を設けていない以上は、コンビニは別業者に入れ代わることも自由に行うことが可能となります。 他方において、事業用定期借地権が賃借権として設定されている場合には、この文言がなくとも民法第612条により、賃借権の譲渡は貸主の承諾を要することになります。地主の立場から考えると、事業用定期借地権の場合には、借地権の譲渡は業態の変更も伴うことが多いので地主の承諾を求めてもよいのではないかと思います。
- 「事業用定期借地権は期限が来ると必ず土地が戻ってくる」ということは、法律の上ではその通りです。ただし、契約期間が満了して土地を返還すべき期日が到来しているときに実際にスムースに土地が戻ってくるかは借地人次第です。期限が到来したのに、借地人がほとんど倒産状態で建物取壊費用も捻出できないという場合には、事実上、借地上に建物が存立したままの状態が続くことになります。法的には、借地人に対し、建物収去土地明渡請求訴訟を提起すれば判決を得て強制執行をすることにより更地に戻すことは可能ですが、それまでに期間と費用を要することになります。 同じく賃料が必ず入るということも、法律上は賃料支払請求権を有しているという意味です。実際に賃料が支払われるか否かは賃借人の経営状態にかかることになります。 要するに、事業用定期借地権は、法律上は更地返還と賃料支払請求権が保障されているということであって、法律通りに借地人が契約を履行するか否かは別問題です。借地人が契約を履行しない場合でも裁判でこれを要求できる権利までは確保されていますが、借地人がこの要求に応ずるだけの支払能力がなければ、権利の実現ができないことになります。
- 事業用定期借地権の登記は必ず行わなければならないものではありません。ただし、登記がなされていれば、誰の目にも借地権の終了時期が明らかになっていますので、契約書を紛失したとか、その後に期間延長の合意をしたはずだといった紛争が生じ難くなるという利点はありますので、借地人がどのような企業であるのか、将来揉める可能性があるのか否かといった観点から、登記の要否を判断されることになると思います。
- 公正証書を作成するが心配がないと言えるかということですが、公正証書を作成するということは、公証人が介在して契約書を締結しますので、将来の思い違いである等の弁解を防止する意味では役に立つと思います。また公正証書は金銭債権については強制執行が可能ですので、その点でも安心だということはできます。ただし、公正証書は金銭債権以外の権利についての強制執行は出来ませんので、公正証書で契約したからといって、公正証書に基づいて明渡しの強制執行はできません。明渡しについては、借地人が期間が満了したにもかかわらず明渡しをしない場合には、別途建物収去土地明渡請求訴訟を提起しなければなりません。したがって、公正証書で全て裁判をすることなく解決できるというわけではありません。
-
地主の立場で考えた場合の、登記の必要性や注意点についてご教授ください。
-
地主側の立場で考えた場合の登記の必要性ですが、登記をしなければ絶対に困るというほどの必要性は地主側にはないと思われます。ただし、前記のとおり、登記がなされていれば、誰の目にも借地権の終了時期が明らかになっていますので、契約書を紛失したとか、その後に期間延長の合意をしたはずだといった紛争が生じ難くなるという利点があるということです。 注意点とすると、事業用定期借地権の期間の延長合意は可能と解されていますので、当初の契約期間を延長する旨の合意をするときは、同時に登記も変更しておく必要があるということかと思います。
-
借主へのアドバイスがあればお願いいたします。
-
事業用定期借地権は、裁判をすれば確実に地主の権利を認めてもらえるという制度ではありますが、借地人の資力や支払能力を保証してくれるものではありません。したがって、契約を締結する時には、「事業用定期借地権だから大丈夫」ではなく、一般の契約を締結する時と同様に、相手方の信用についての判断をしっかり行うことが重要です。その上で、借地人が破産等の事故がない限りは、確実に地主の権利を実現できるのが事業用定期借地権であると考えて戴いた方がよいと思います。 また「借地権の譲渡については地主の承諾を得る」との文言がないとのことですが、事業用定期借地権の場合には承諾を要する旨の文言を付することも検討されてもよいのではないかと思います。もっとも、借地人側が20年内であっても第三者に事業用定期借地権を譲渡する可能性が高く、地主の承諾を求められるのであれば契約に応じられないというのであれば、そうした相手方の条件を考慮して承諾を要しないとの条件に応じてまで契約を締結するか否かを含めて検討される必要があると思います。
第28回(2011.02)
事業用定期借地権の延長合意についてお尋ねいたします。
-
地主・借主の相互合意がある場合、期間満了後に数年ほどの存続期間を延長する際は簡易な覚書で問題ないか?
-
事業用定期借地権の延長合意は有効と解する見解が多数であると思います。しかし、延長の手続き等については判例があるわけではなく、定説が存在していません。契約自体を公正証書で締結していれば、その存続期間の延長は簡易な覚書でもよいとの考え方もありますが、存続期間は定期借地契約の中でも重要な事項であるから、法が事業用定期借地権については公正証書による締結を義務付けていることからすれば、延長契約についても公正証書によるべきだとの見解もあります。 したがって、判例が存しない現状では、公正証書による合意をすべきかと思います。
-
期間の延長は何年まで可能か?
-
期間の延長は何年まで許されるかとのことですが、法理論的には延長は事業用定期借地権の許容された存続期間までということになるはずです。その意味ではトータルの期間が50年未満までは可能なはずですが、事業用定期借地権の最短期間である10年以上の延長をするのであれば、同期間以上の再契約を締結すれば済むことですから、延長は再契約ができない場合に留めておくべきものと思われます。よって、延長期間は最長でも10年未満と考えたほうがよいと考えます。
-
3年の期間延長の希望を地主に話し了解を得た上で、中途解約の特約条項を盛り込んだ10年の事業定期借地権で公正証書を作成し再契約。そして、借主は3年後に中途解約の特約を利用し契約を解除することは可能か?
-
10年の事業用定期借地権の再契約を締結する方法は、地主が同意すれば可能ですが、地主側からすれば、10年の事業用定期借地権を設定した以上、借地人側が任意に解約しない限り、地主側は解約の余地がなくなるため、万一の場合には10年間の継続使用を許容するつもりがない限りは同意することは難しいと思われます。